環境変われば病も癒える

80代♀
10年来の難治性の三叉神経痛(第3枝)
ガンマナイフも無効
患側”後谿”20分置鍼で
流動食からお粥が食べれるように痛みは緩解
ひとりで話し昼間は相手がいない引きこもり日々から
老人ホームに入居して、同じ世代の仲間との共同生活
これで病にばかりココロを囚われた生活が一変した
今では普通食をしっかり噛んで
美味しく三食食べれるようになった
来院の度に表情が明るくなり
嬉しそうに毎日の生活を語る笑顔から
病が癒えたことを確信した

80代♀
10年来の難治性の三叉神経痛(第3枝)
ガンマナイフも無効
患側”後谿”20分置鍼で
流動食からお粥が食べれるように痛みは緩解
ひとりで話し昼間は相手がいない引きこもり日々から
老人ホームに入居して、同じ世代の仲間との共同生活
これで病にばかりココロを囚われた生活が一変した
今では普通食をしっかり噛んで
美味しく三食食べれるようになった
来院の度に表情が明るくなり
嬉しそうに毎日の生活を語る笑顔から
病が癒えたことを確信した

小学校の先生の話
発達障害を認めたくない親がいる
親の多くはイライラして
子供の接し方も優しさがない
幼児のころからそういった接し方をしていると
子供の成長に悪影響があるのは必然
発達障害の子供を受け入れ
子どもの個性と認めて
大人が優しく接することで子供は癒される

久留米市での事例
「すくすく発達障害教室」は久留米市が平成19年、20年度に
文部科学省の「発達障害早期支援モデル事業」指定を受け
発達障害児の早期発見、早期支援を目的として始まり
モデル事業終了後もそのニーズの高さににより
久留米市独自の事業として継続されているとのこと
「すくすく発達障害相談教室」は週に1日市立小学校の通級指導教室において
小児科医師、通級指導教室担当教員、臨床心理士が相談に応じている
個々のケースについて医療、教育、心理の多職種の連携の下
子供を評価、その後の支援の方向性をアドバイスしていることが特徴
地域の支援に繋ぎ、地域の中で子供達やその保護者が孤立しないような
支援体制が大切と考えられた素晴らしい制度
お手本にして、名古屋市も同様な制度の検討を急ぐべきだ
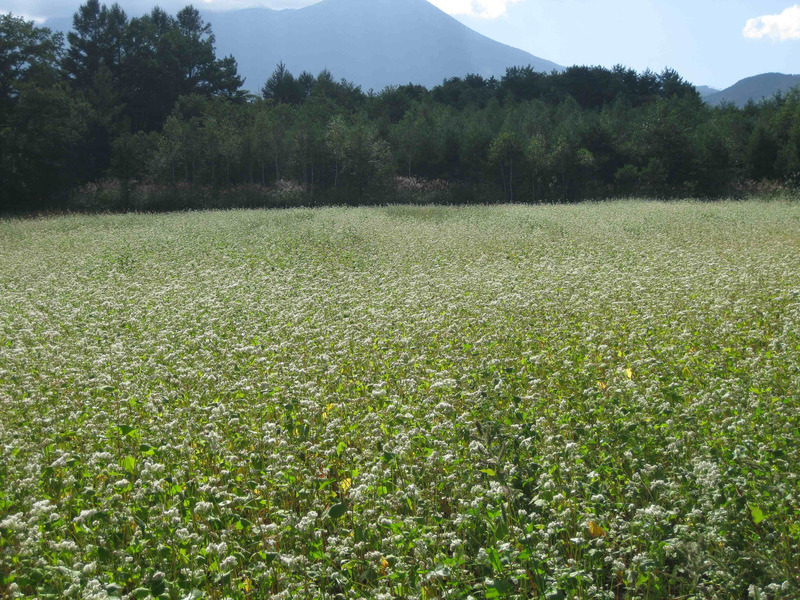
小児の発達障害は最近マスメディアでも取り上げられるようになってきた
平成24年度に文部科学省が行った質問紙による調査では
通常学級に在籍する児童の6.5%と推定されている
これらの子供たちは外見上は通常の子供と区別はつかず
障害もあるようには見えないために周囲の誤解を受けたり
イジメや仲間はずれになったりすることがしばしばある
そのために子どもたちは大きなストレスにさらされ
気づかずに放置されると二次的に、うつ、反抗挑戦性障害、チック
などの併存障害が高頻度で出現することが知られている
近年、発達障害児の早期発見、早期介入、適切な対応により
発達障害の子供たちが社会生活に適応しやすくなり
併存障害が予防できることがわかってきた
以下次回に

(公社)全日本鍼灸学会学術大会(九州大会)
スタッフ6名と2日間参加した
症例や研究報告の演題が279題
大会場でのシンポジウムや基調講演、セミナーが10題
実技セッション3題
ランチョンセミナー2題
その他ワークショップ・市民公開講座と盛り沢山であったが
最も印象に残っ講演は、我々と流派は違うが
鍼灸臨床50年の首藤傳明先生の言葉だ
「以下要約」
毎日の臨床の理想の姿として
天皇陛下の心臓手術を担当した順天堂大学心臓血管外科教授
天野篤氏の言「手術中は頭を使っているのは15%くらいです。
85%くらいは反射的に手を動かさないといけない。
例えばピアニストに似てますよね。今弾いているところの
先の楽譜を見ているように、外科医は手術の先にあるところを見ています」
脈を診る、腹診をする、皮膚を触診する、経穴を探る、
鍼を持つ指がしなやかに動き、頭で考える前にツボに
指が止まり、鍼を打つ。勿論理論的な裏付けがなされた上で・・・
技術は突き詰めるとき”技”ではなく”道”に達する
プロフェッショナルとはかくあるものと思っている
僕は不器用なので、並み鍼灸師の3倍努力している
日々全力投球、精進を続ける大先輩の言葉は重い
(公社)全日本鍼灸学会HP http://www.jsam.jp/
大会内容の演題を見ることができる

ART(体外受精)と鍼灸を併用して妊娠した症例
30歳
27歳で結婚自然妊娠に至らず
人工授精4回
体外受精3回
いずれも妊娠に至らず
鍼灸治療を開始し4回目の体外受精が成功
妊娠確認される
ART単独での妊娠から出産に至る(生産率)は
20歳台から32歳ぐらいまでは
ART(高度生殖医療)をもってしても20%程度でしかないが
鍼灸治療が介入することによって
50%以上に生産率が上がるのである
http://www.n-acop.com

わが国のART施設の情報開示の現状
わが国ではART実施施設は
日本産婦人科学会への登録と臨床成績の
自主報告が義務付けられている
しかし、各ART実施施設の情報は開示されていない
ART登録施設において適切な情報をHPに掲載しているのはごく少数である
不妊カップルの自律的意志決定を尊重するという観点から
欧米で採用されている各医療機関の個別情報開示も求められるのではないか
この意見は日本生殖医療協会会長
国際医療技術研究所 IMT College 理事長 の荒木重雄先生が
不妊カウンセラー養成講座で述べられた内容を引用しています

高齢出産のリスクファクター
ART(高度生殖医療)による妊娠率は
37歳までは約20%
38歳から急速に低下し
44歳以上では5%未満でしかない
ARTにより妊娠して最終的に”出産”に至る確率は
36歳までは約15%
37歳から急速に低下し
42歳以降では5%以下
42歳は3.7%
43歳は2.0%
44歳は1.3%
45~46歳は0.6%
47歳は0.1%である
妊娠当たりの流産率は
35歳では20.3%
40歳で35.1%
41歳で42.3%
42歳で46.5%
43歳で55.2%
44歳で58.1%
45歳で64.6%
46歳で70.2%
47歳で80.0%
この数字をどう捉えるかは個人の価値観もあるが
45歳以上で生児出産に至るものは1/200以下に留まることから
ARTの対象とすべきでないとするのが妥当と考えられている
以降は次回に続く・・・
【臨時休診のお知らせ】
6月5日(水)臨時休診です
6月6日(木)診療します
6月7日(金)診療します
6月8日(土)鍼灸学会学術大会の為休診です

昨日まで東京で日本不妊カウンセリング学会に参加したので
その報告を・・・
ART(高度生殖医療=体外受精・顕微受精・凍結融解杯移植)
を受けるひとはこの10年間で急増している
2010年のデーター
体外受精 67,000件
顕微受精 91,000件
凍結融解胚移植 84,000件
合計 242,000件
ARTによる出生児数は 28,945人
これは一年間の全出生児の2.8%で
36人にひとりが生殖補助医療で生まれていることになる
今やクラスに一人は不妊治療を受けて生まれた子供だ
但し、晩婚化に伴い不妊治療を受ける人の高齢化が進み
40歳以上でARTを選択する人の割合は(不妊治療を受ける人のなかで)
2008年 32.1%
2009年 34.4%
2010年 35.7%
と年々増加している
しかし、40歳以上で妊娠する確率は低く、
技術が進歩したこの10年間でも”不変”である
ARTを受けているひとで妊娠した人の割合は
40歳 7%
44歳 1%
但しこれは流産、死産により出産に至った数字ではないことに注意
※次回は高齢出産のリスクを述べるが・・・
有名人の高齢出産がマスコミで華々しく取り上げるので誤解を招く
「40歳を過ぎて妊娠出産に至るのは稀である」
という正しい情報はあまりにも少ない
結婚する女性の平均年齢が30歳に達した今
大切なことは子供が欲しいカップルは
「結婚したらすぐに子作りに励みなさい!」と声高に教育することだ

気が上に昇ることを”気逆”という
専門的には様々な要因に分類できるが
気逆の与える身体の現象は多彩で苦痛を伴う
顔がかっと熱くなる
頭痛・目眩・耳鳴り・目の充血・頚肩こり
動悸・胃のむかつき・咳etc・・・
こういった傾向がある患者さんは
カフェインの摂取を控えめにした方が良い
「主な飲み物のカフェイン含量」※150mlはコップ1杯くらい
種類 量 カフェイン量
コーヒー(炒り豆・ドリップ) 150ml 100 mg
コーヒー(インスタント) 150ml 65 mg
コーヒー(エスプレッソ) 40ml 77㎎
コーヒー(カップチーノ) 150ml 50 mg
コーヒー(ノンカフェイン) 150ml 1 mg
玉露 150ml 180 mg
抹茶 150ml 48 mg
紅茶 150ml 30 mg
せん茶 150ml 30 mg
ほうじ茶1杯 150㎎l 30㎎
ウーロン茶 150ml 30 mg
番茶 150ml 15 mg
玄米茶 150㎎l 15㎎
麦茶・黒豆茶・杜仲茶・ルイボス茶など 150ml 0 mg
ホットココア 150ml 50 mg
コーラ 350ml 34 mg
コーラ(ダイエット) 350ml 45 mg
栄養ドリンク(カフェイン入り)100ml 50 mg
板チョコレート 50g 20 mg
上記の資料を参考に”気逆”がおきやすい人は
多くても日に1~2杯に留めておくべき
〒468-0023
名古屋市天白区御前場町(ごぜんばちょう)13番地
(052)804-8190
月:AM9:00-11:30、PM3:00-7:00
火:AM9:00-11:30、PM3:00-6:30
水:AM9:00-11:30、PM3:00-6:30
木:休み
金:AM9:00-11:30、PM3:00-7:00
土:AM9:00-11:30、PM2:00-5:00
日:休み
祝日:AM9:00-11:30、PM2:00-5:00
該当する方を選択してください
